婚姻中に、一方の配偶者が不動産を購入する際、住宅ローンの連帯債務者・連帯保証人になったり、それ以外の借入時に連帯保証人や保証人になったりすることがあると思います。
こういった、結婚期間中の保証契約が離婚の際にどう清算をするかで問題になることについて、以前別の項目でお話したとおりです。
今回は、離婚したあとに、上記のように自分の意思によらず、勝手に一方の配偶者に保証契約を締結されていたような場合、他方の配偶者は、保証契約に基づく支払いを求めてきた金融機関に、自分には身に覚えがないから支払わない、といえるかどうかについてお話したいと思います。
通常、こういった保証契約を締結する際には、金融機関の窓口などで担当者が契約をしようとする者の意思を確認しながら、手続きを進めるのは一般だと思います。
ただ、中にはその配偶者の代理人と自称する者が窓口に現れ、手続きをした場合・あるいは契約書を郵便でのやりとりで交わしていることもあるのではないかと思います。
そういったときには、筆跡がその配偶者の者といえるかどうか、照らし合わせた上で、保証契約を争う元配偶者から、どういうやり方・態様で他方の配偶者が偽造をしたと考えるか、金融機関に具体的に説明する必要が出てきます。その上で、金融機関内の記録と照らし合わせてみて、整合すれば、身に覚えがないから支払わない、という主張も認められやすいように思えます。
ただ、契約締結後に、金融機関から保証人となっている(元)配偶者に対して、保証している債務の残高を通知していたり、その後の取引の中で保証債務の存在を(元)配偶者に伝えていたりしていたにもかかわらず、(元)配偶者がそのまま何も異議を述べていなかったようなときには、場合によってはあとから保証契約は知らないと争うことが難しくなることがありえます。
ただ、夫婦の間であれば、実印の持ち出し、印鑑証明書を持参しての契約締結もありうるでしょうし、そもそも夫婦であるのだから、たとえ来ていなくてもその配偶者の承諾はあっただろうと当然にいえるのではないか、という金融機関の反論も予想されるところです。
しかし、たとえ夫婦の間とはいえ、実印・印鑑証明書の持参だけで一方から他方の配偶者に代わりに契約を結ぶにあたって代理権を与えていた、と簡単にみるべきではないでしょう。特に金額が大きい借入や住宅ローンであれば、必ず金融機関から、他方の配偶者に、本当に保証人になる意思があるか、きちんと確認する必要があるでしょう。
次回に続きます。
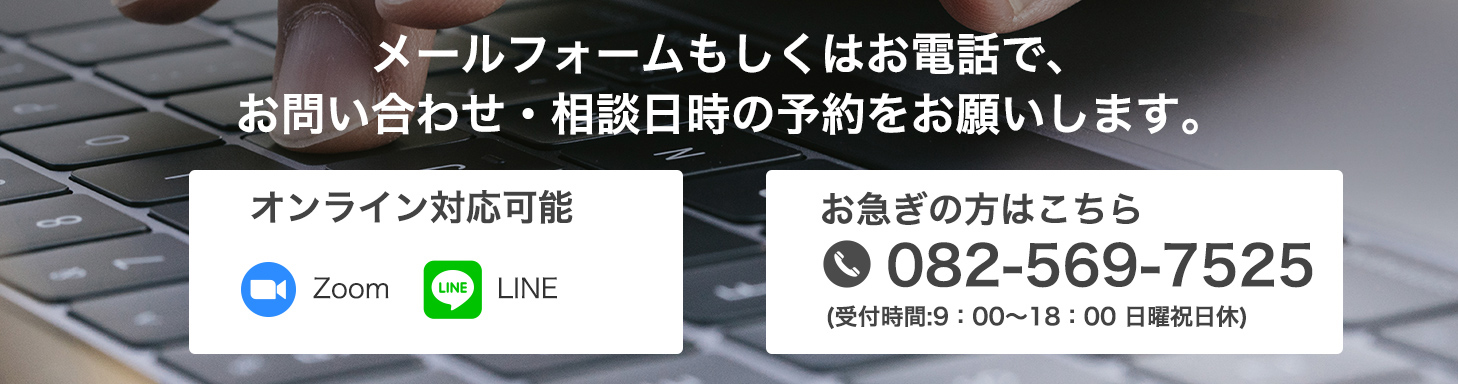
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。

© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.