親が特定の兄弟あるいは全くの第3者に財産を遺言あるいは生前贈与で全ての財産を渡している場合には,遺留分と呼ばれるものを侵害している可能性があります。遺留分とは,簡単に言えば亡くなった方の配偶者や子供に対して生活保障などのために認められているもので,遺言でも完全に排除することはできません。その割合は,法律で定められています。計算方法や対象となる生前贈与の種類(相続人に対する贈与については少しわかりにくいながら改正がなされています)
遺留分侵害(減殺)請求という遺留分侵害に対する権利行使は行使をしないと意味がありません。遺留分に該当する割合は当然に確保されているものではありません。相続が始まり・侵害を認識してから一定の期間の間に,侵害をしている方(遺言や生前贈与で大半の財産をもらった方等)に対して,「遺留分侵害請求(改正前は遺留分減殺請求)を行う必要があります。別のコラムも触れましたが,特にこの方法でやらなければいけないという方法は決まっていませんが,証拠で残るようにしておく(内容証明郵便を送る等)をしておかないと,後々面倒なことになりかねません。
具体的な計算例は別のコラムで触れていますが,遺留分率は亡くなった方の親が権利者のみである場合には1/3・それ以外(配偶者や子供がいる場合)には1/2となります。
実際に,こうした権利を行使した後の問題は,改正前では少数の持ち分を持つ形(遺留分の権利を持つ側から見た話)であったため,生活保障という遺留分の意味にそぐわない・遺言をしたなどの意思が反映されないという問題がありました。改正によって,お金の清算という形になりましたが,遺留分審が請求を行うほかにお金の回収についても別途時効がありますので,注意が必要です。
また,遺留分の減殺請求によって効力を否定する順番などが法律で決められていました。それによると,遺贈⇒死因贈与⇒生前贈与の順番で,前の順番の効力を否定して遺留分侵害がなくなるのであれば,その次の順番のものは効力を否定されませんでした。同じ順番のものは遺贈された者同士はその価額による・生前贈与であれば,最近のものから順番にさかのぼるというものでした。遺留分の侵害請求になった後はお金での清算を求めることになりますが,遺贈と生前贈与が存在した場合(遺贈が複数存在する場合や生前贈与が複数存在する場合も同じ)に,どちらからお金の支払いを負担するのかは同様に問題になります。言い換えると,誰に対していくらのお金の支払いを求めるのかという話になります。
こちらについても,遺贈⇒死因贈与⇒生前贈与,生前贈与は最近のものからさかのぼっていく,遺贈同士・同じ時期になされた生前贈与であれば贈与されたものの価額に応じてという点は変わっていません。お金の支払いを求める相手は遺贈を受けた方から請求をしていくことになります。先順位の方に対する請求(遺留分侵害をしている額を請求)で侵害が解消されれば,次の順位の方へは請求はできなくなります。
遺留分の計算を行う上では,対価を支払ったうえでの売買ではあるが時価から見て著しく低い金額であるもの・贈与であるが一定の義務を課されているものが存在します。これらについては,改正前から,見合わない金額分・一定の義務の価格評価分を差し引いたものが,遺留分侵害を考える上での贈与に組み込まれてきました(ただし,改正前は一部効力否定という問題がありました)。ここは改正後も変わっていません(法律の文言上は負担付贈与の場合に統一されています)。
ここで問題となるのは,負担という義務の評価や売買などを行う際の著しく低い金額とはどこから言えるのかという点です。基準は取引時価から見てということになります。取引価格がはっきりしている上場株式や不動産では時価がはっきりしています。非上場株式については株式の買い取り請求権の際の評価や相続税の評価額を算定する際の基準(財産評価基本通達に定められた,株主の地位や会社規模などにより算定方法を決める方法,純資産方式や配当還元法などがあります)などが参考にされますが,当然にこの金額で問題がクリアされるのかという点が問題として残ります。
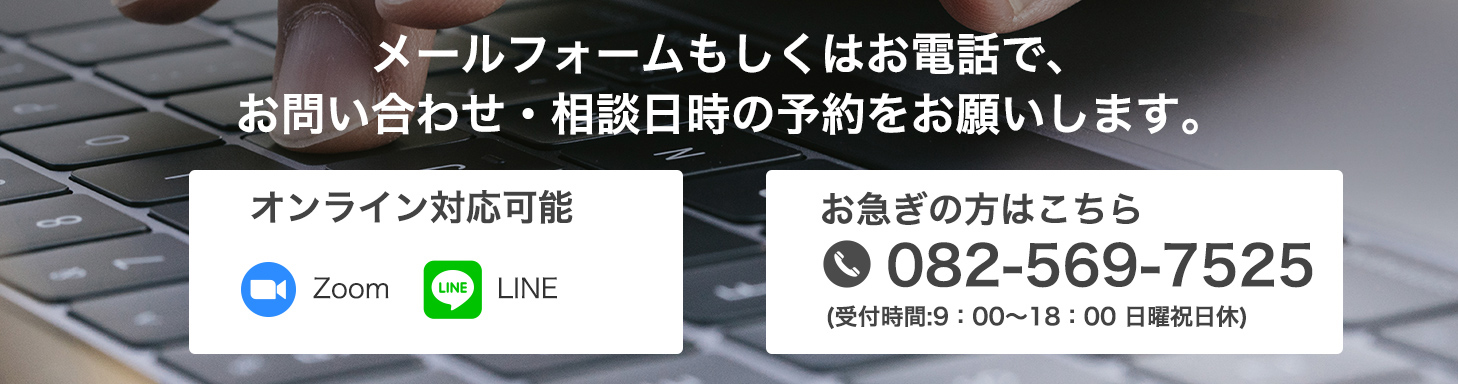
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。

© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.