前回、法律上遺言の内容を撤回したとみなす場合について、①前の遺言と内容の抵触する遺言がされた場合、②遺言と抵触する生前処分がされた場合の二つについて、お話ししました。
今回は、法律上、以後が撤回とみなされる残りのケースをお話ししたいと思います。
遺言者が、自分で一旦作った遺言書を破ったり、焼き捨てたりしたのであれば、元書いた遺言書とおりにするつもりがないといえることから、前の遺言を撤回したものとみなしているのです。
この、「破棄」には、遺言書の文面をマジックや線で消したりして内容が分からなくすることも含みます。きちんと文面が消されておらず、元書かれている内容が読み取れる場合は、「破棄」といえず、遺言書に後で付け加えたり、訂正したものとみるのが一般です。たとえば、自筆証書遺言の場合、加除その他の訂正をするには、場所を示し、変更をした旨記載して署名し、変更の場所に印鑑を押さなければならないとされています。ですから、自筆証書遺言で単に文字を抹消しただけであれば、元の文言によることになるので、注意が必要です。これに対して記載の変更をしているけれども,訂正などの法律上の要件(変更した旨の記載やその場所への押印等)を満たさない場合には,元の文字を読み取れれば元のままとされることもありますが,その内容の重みと訂正内容によっては元の記載内容を含めて無効になる可能性もあります。仮に変更をする意図があるのであれば,その記載などで後で無効になるなどの問題が出るのかをきちんと注意をしておく必要があります。自筆証書遺言については手軽に作れる半面で法律上無効になる場合が形式面を含めて多数存在するので,注意が必要です。
また、遺言書の破棄は、作成した遺言者自身によらなければなりません。第三者が破棄したときは、それが遺言者の遺志によることが必要です。
それから、「故意に」(わざと)が要件なので、誤って(過失で)破ってしまった場合はあたりません。ただ、結局のところ読めなくなってしまえば、撤回したのと同じになるでしょう。
遺言書自体の破棄が必要なので、公正証書遺言のように、公証人役場に備え付けられている場合、手元の正本を破棄しただけでは
「破棄」にはあたらないとする裁判例があります。この場合は、公証人役場に連絡をし、原本も破棄してもらわないと「破棄」とはいえないでしょう。
自分の死後他人にあげるつもりであった物をわざと壊したりしてしまうのであれば、そもそもあげるつもりが無くなったとみるのが自然であることから、遺言を撤回したとみなされます。
遺言者でなく、第三者が壊してしまったときは、遺言者がその第三者に対してもつ、価値相当分の金額を支払うよう求める権利を遺贈の目的物にしたと推定されます。
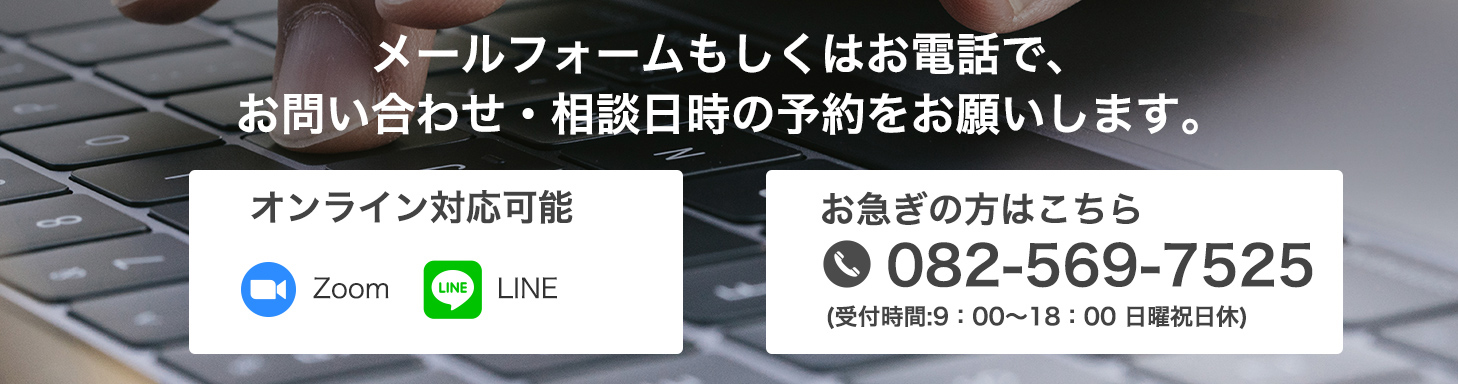
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。

© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.