遺留分の侵害がなされているのかどうかという点は計算方式が法令上定められています。平成30年に改正された内容では計算方式が明確化されるようになりました。その計算式は,遺留分率(親のみが権利者の場合は1/3,子供・配偶者については1/2)で法定相続分率に応じて,各人の実際の遺留分の比率が決まります。
計算方法は,他のコラムでも触れていますが
基礎財産額=相続開始時に存在した財産(遺贈の金額も含む)+生前贈与された財産で考慮対象のもの
-被相続人が負っていた負債金額
各人の遺留分額=基礎財産×各人の遺留分率
遺留分侵害額=各人の遺留分額ー遺産分割で取得する金額(具体的な相続分)-その人が遺贈や生前
贈与で得たお金+その人が負担することになった被相続人の負債金額
でプラスになれば,遺留分侵害を受けていることになります。
今回は,被相続人の負債金額について触れていきます。基礎財産額を考える上での負債とは,被相続人が負担している負債です。ここでの負債は借り入れや契約上のほかの支払い義務・賠償金支払い義務・税金や罰金の支払い義務は含まれますが,いわゆる保証人としての負債は原則として含まれません。これは,連帯保証人であっても,保証人に対して最初に請求されるとは事実上限りませんし,支払った金額は求償といって本来の債務者などに請求ができるからです(連帯保証人同士の間の求償には限度があります)。したがって,負担が不確実であるため,本来の債務者に支払い能力がないなど確実に負担をしないといけないケースを除き,当然にはここで差し引く金額には含まれません(こうした趣旨を述べた裁判所の判断が存在します)。
ちなみに,相続税の計算を行う際の「債務控除」(同じく主には被相続人の負債を差し引くもの)についても,同様の理屈から保証人としての負債は原則は差し引かれません。
次に遺留分侵害額を考える上でプラスする負債額についてです。法律上,負債金額は何もなければ,法定相続分に応じて相続することになります。これに対して,協議や遺言によって負債の引継ぎも指定をすることが可能です。例えば,収益用不動産をある相続人に「相続させる」との遺言を記載し,その物件用の借り入れを「相続させる」相続人に引き継がせると遺言で起債をする場合です。こうしたケースでは,他に負債がある場合には,どのような引継ぎになるのかを明確にしておいた方がトラブルは防げます。解釈の余地をなくすことが,意向を反映しやすくなるためです。
最高裁の判断の中では,遺言で示された意向の解釈として,「すべての遺産を○○に相続させる」という趣旨の内容である場合には,その「○○」にマイナス部分(負債)も引き継がせる意思であったと解釈されるとしていますので,この場合には負債の引継ぎが明確になります。この場合は遺留分の権利者は全く負債を引き継がず,「○○」の負担することになった負債額が被相続人の負債額全額になります。ただし,被相続人の債権者には遺言の内容は当然にはわかりませんから,知らない債権者には法定相続分に応じた負債の支払いをする⇒その後に「○○」に対して支払ったが金額を請求するという流れになります。ただし,こうした流れになる場合には「○○」の支払い能力がない場合もありえますので,その場合は回収リスクをほかの相続人が負うことになります。
いずれにしても,この解釈はあくまでも「すべての遺産を特定の相続人に相続させる」という遺言の場合に話になります。
また,被相続人が負担をすることになったという債務には,相続開始の前後を問わず,相続させるなどと指定された方が,被相続人の負債支払いなどをした金額は考慮されません。しかし,実際上は支払いの負担などを行っているので,この金額が何も考慮されないのはおかしな面もあります。法律上は,被相続人の負債を支払った・債務引き受け(面積的債務引き受け,債務者を交代する)などの負債を減らす行為をした場合には,その金額の範囲内で遺留分侵害額が減るという規定を置いています。ここでの減らす行為には相殺なども含まれます。
このようにマイナス部分がどうなるのかも確認しておくことは重要です。最後に,先ほどの計算をしてみると,そもそも基礎財産の計算をしてみるとマイナスになってしまう(被相続人が債務超過であった)場合にどうするのかという問題が出てきます。この場合,計算そのままであると遺留分侵害は確実にゼロになるためです。
この問題については見解が分かれています。3つの見解があるとされます。一つ目は文字通り遺留分侵害はないと考える考え方・二つ目と三つめは考えの筋道に違いはあるものの,贈与分があればその部分で遺留分侵害があったと考えるものです。結論が異なるところですが,確定した裁判所の判断が存在するわけではありません。実際に問題となった場合にはこうした状況も踏まえてやり取りをすることになるでしょう。
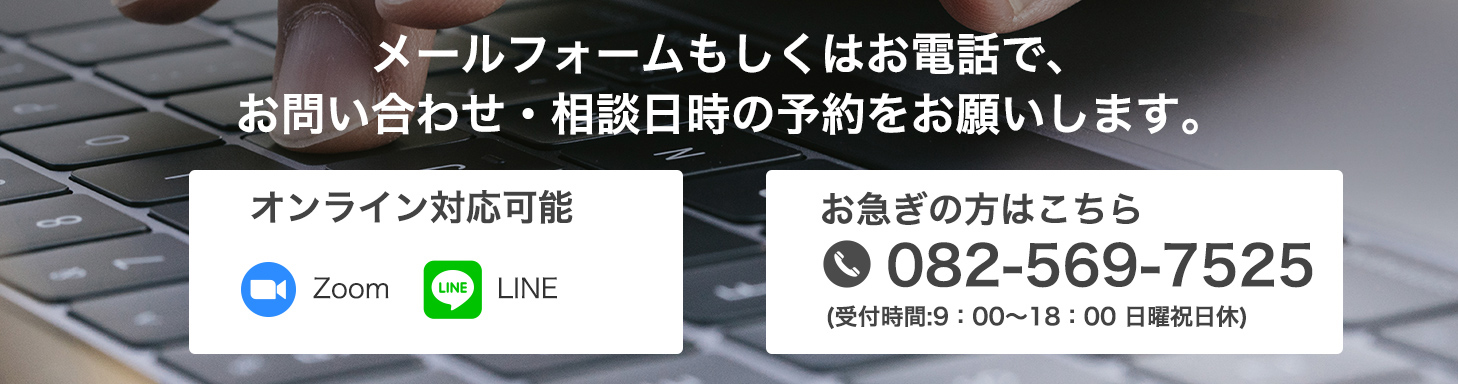
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。

© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.