仮登記と言ってもなじみない制度ですが,法律上2つの種類が定められています。一つ目は,登記申請をすることはできるが書類の一部を提出できない場合にするもの(1号仮登記と呼ばれるもの)・将来登記請求できる権利を保全するために行うもの(2号仮登記)と呼ばれるものが存在します。登記請求を行うことができるだけの状況である場合に問題が生じることがあるので,今回は後者について触れていきます。
何が問題かと言えば,仮登記をそのままにしておいた場合に,登記を請求できる権利自体が時効によって消滅してしまう可能性があるという点です。仮登記は,将来登記請求に応じて登記がなされた段階で登記簿における順位を保全する(簡単に言えば,仮登記された段階での順位を「予約」する)意味合いを持っています。ここでいう「予約」とは順位を確保するという意味で,なぜこれが必要かと言えば,あとで登記請求をする権利に基づき権利移転してもらうものと矛盾する登記がなされた場合に,自らが優先することを主張できない等の事態が生じかねないためです。登記は確保された順位におくれるものは先のものに対して権利を主張できないので,順位確保は重要な意味を持ってきます。
問題になる場面として一度売買をして再度買い戻しの特約を結んで置く場合や農地法の許可を受けることを前提にこうした仮登記をしておく場面が挙げられます。前者は買い戻しの特約があっても登記をしておかないと順位を確保できません。後者は農地は法律上売買等をする場面では都道府県におかれる農業委員会の許可がないと売買の効力が生じないとされていることや許可の申請に手間と時間などがかかることから,順位を確保しておく必要があります。こうした理由から仮登記がなされることがあります。仮登記をしておけば後で矛盾する売買などがなされても順位が確保されていることで権利の主張ができるためです。前者については特約通り買戻しが行われ登記が行われる場合・後者ではきちんと許可をとって名義の移転ができれば問題はありませんが,そうならず仮登記のみが残る場合には問題が出てきます。
登記を請求する権利自体も時効にかかるため,時効に必要な期間を経過してそのままである場合には時効にかかってしまいます。この事項に必要な期間は民法の改正もあり,令和2年3月までの契約に関わるものは権利を行使できるときから10年間で時効にかかります。令和2年4月以降のものは,原則として契約から5年で時効にかかります。厳密には,権利を行使することができることを知ってから5年ですが,通常は契約時にいつ権利を行使することができるかははっきりしていることが多いため,このようになるケースが多くなろうかと思われます。
そのため,亡くなった方が行った売買について特に何らかの理由で農地法の許可が取れずに時間が経過した場合などには相続で引き継いだ方が名義を移すどころか,仮登記の抹消を売り主から求められる可能性もあります。時効により登記移転を求める請求権が消滅したという理由によるものです。もちろん,話し合いによって何かしら解決を図ること自体は可能ですが,リスクが出てくる点には注意が必要です。可能であれば,農地法の許可は受けれるかどうかを早めに確定して後に問題を残さないようにしておくことが重要です。
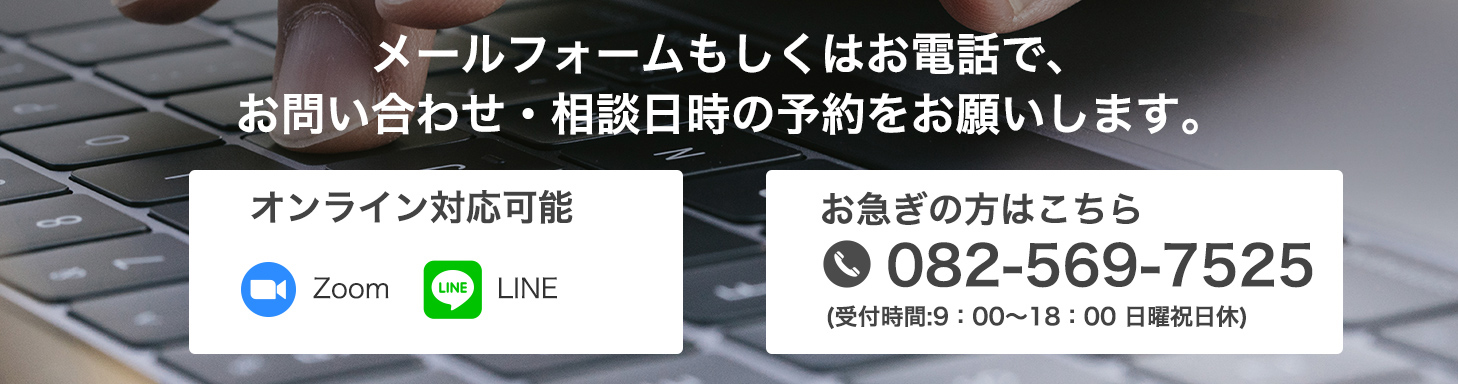
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。

© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.