相続財産のうちの宅地等の評価に関する特例である小規模宅地等の特例等については法律の定めがあり,その要件を満たす必要があります。亡くなった方と同居をしていない別居の親族が相続を行う場合に,生活の根拠地や事業を行うために利用制限が事実上経済的価値が下がる点を考慮する必要があまりないことから,その適用が制限されています。
亡くなった方と別居の親族が相続人としてこの特例の適用を受けるためには,亡くなった方の配偶者やその他同居の親族がいないこと・相続開始の時点から相続税の申告(この特例が問題になるのは相続税の申告が必要なケース)の間その宅地等を継続して保有していること(つまり,売却した場合は除きます)・特例の適用を受ける別居の相続人が相続開始時点で所有していないこと・相続開始前3年以内に適用を受ける方やその一定範囲の親族などが所有する家に住んだことがないこと,が要求されています。
相続税に限りませんが,課税処分(申告税金額が足りない場合・申告をしていない場合)や更正の請求を認めない処分(一度納税した後税金額が高い点を争う等の場合)に争う方法としては,裁判の前に国税不服審判所での手続き(処分をした税務署長に再調査の請求を行うことも可能)背争う方法が制度上定められています。そもそも,これらの争う手続きの前になされる行政からの処分の前に税務調査と呼ばれる手続き(行政指導という任意の協力を求める形で行われるものや国税通則法という法律で定められている手続で行われるものが大半かと思われます)
この国税不服審判所での判断(裁決)の中に,相続放棄を配偶者が行った場合に,別居の子どもが小規模宅地等の特例を使って宅地等の評価を行って相続税の申告を行ったことについて,この特例が使えないから税金が多くなるとしてなされた処分を争ったケースへの判断が存在します。この特例が使えないと財産評価を下げることができませんので,納税額不足と少ない申告へのペナルテイで納税額がより増えるというのがここでの問題点です。
ここでの争点は,相続放棄を行った場合に配偶者がいても最初から相続人とはならないと法律で定められていますが,このことが小規模宅地等の特例の要件との関係で影響があるのかというところになります。非常に条文自体は読みにくいですが,「特定居住用宅地等」として定められた居住用の宅地等の特例の要件を定めた条文では,配偶者や同居の親族が相続開始時点(被相続人がなくなる時点)でいないことが必要とされています。
ここで「いない」ということの意味が相続放棄で相続人ではなかったということで満たされるのかどうかが問題になります。今回触れる裁決(国税不服審判所平成31年3月29日採決)では,満たされないと判断しています。その理由として,相続放棄を行っても配偶者は生存している・相続人で亡くなったにすぎないからという点が挙げられています。税法関係で用語の意味をどう考えるのかは問題となる点ですが,一般に特に別に考える理由がなく言葉の意味の特別ルールもなければ,民事上の言葉と同じように考えると一般にはされています。そこからすると,配偶者は離婚をしない限り(死亡後は姻族終了をしない限り)は相続放棄をしても変わらないことからすると,この判断にも相応の理由があるかもしれません。
ちなみに,社会保障関係や比較的最近の最高裁の判断(最高裁令和3年3月25日判決,中小企業退職金共済に関する配偶者の意味)では,遺族の生活保障などの目的等の制度趣旨から配偶者の意味を考慮しています。言い換えると,そうした制度趣旨からして別に考える理由があるかどうかという点がなければ,配偶者の意味は変わらないことになります。
特例を使うかどうかは納税額が大きく変わりかねない(プラス少ない申告額の場合にはペナルテイ部分を受けるリスクがあります)点がありますので,要件を満たすのかどうかをよく確認しておく必要があります。
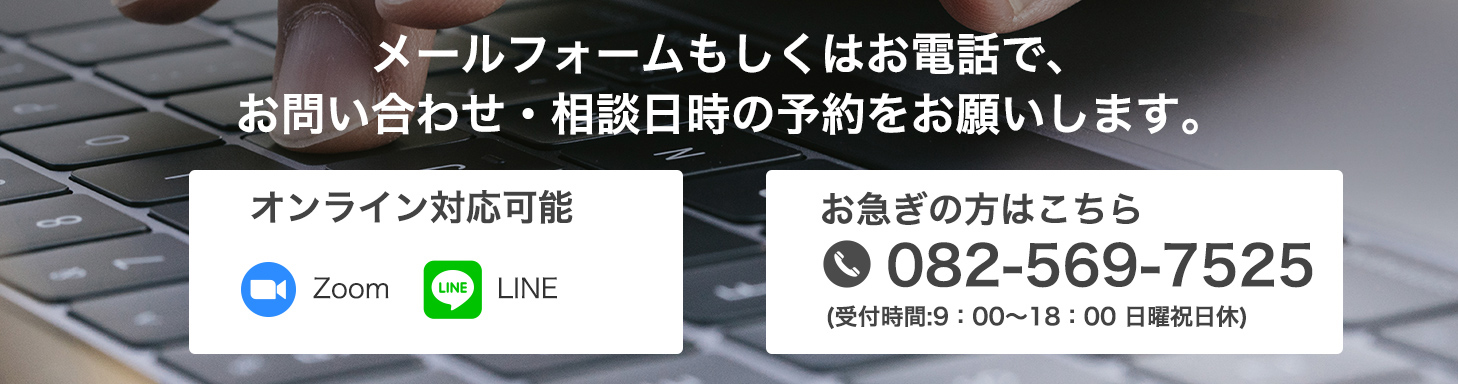
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。

© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.