亡くなった方が残した負債は法定相続分に応じて当然に相続されるのが原則です。したがって,亡くなった方の法定相続人は他に何もなければ,法定相続分に応じて負債を引き継ぎます。未払いの税金であっても,税金を支払う負債が残りますので変わりません。他に遺言で何かしらの負債を引き継ぐなどの点があれば,この部分を含めて考える等変わるべき点はあります。ただ,遺言で決めた負債の引継ぎの内容は当然に債権者(税金は税務当局)に主張できるわけではなく,原則は相続分に応じて支払い後で相続人の間での負担を調整する形になるでしょう。
これに対して,遺言で贈与を受ける遺贈であればどうなるのでしょうか?包括遺贈と呼ばれる全ての遺産あるいは全遺産のうちの一定割合をもらうようなケースでは,相続人と基本的には同じように考えます。別のコラムでも触れていますが,包括遺贈の場合には遺贈を断るためには相続放棄の手続きをとる必要があります。期間制限や申立先(家庭裁判所)に注意をする必要があります。この手続きをとった場合は負担がない反面・プラスもなくなります。これに対して,特定遺贈の場合には,遺産の中の一部の財産の贈与を受けるだけですので,相続人や包括遺贈を受けた方とは状況は異なります。負債をすべて引き継ぐわけでも一定割合を引き継ぐわけでもありません。相続放棄のように期間制限付きの手続きをわざわざとる必要もなく,単に遺贈を受け入れない意思を示せば足りることになります。受け入れなければ,プラスもマイナスもない点は包括遺贈の場合と異なりません。
包括遺贈の場合には,遺贈を受けて取得した財産の範囲で相続人と同様に負債も引き継ぎ,未払い税金を納める義務が生じます。これに対し,特定遺贈の場合には先ほど触れたように負債を基本は引き継ぎませんので(負担付きで引き継ぎを受ける内容であれば別)未払い税金を納める義務も負わないのが原則です。
ただし,法律上,本来税金を納めるべき方が納税しない場合に,納税義務を法律上課される第2次納税義務を課される可能性はあります。ややこしい話ですが,基本的には本来税金を納めるべき方が納税しない部分(要は不足部分)でかつ,遺贈により受けた利益が現存する範囲で納税義務を課されるというものです。法律上,未払い税金の納期前1年以降になされた贈与等の行為についてが規制対象となり,遺贈以外であっても,贈与・時価を大きく下回る場合の有償譲渡も含まれるとされています。したがって,実は遺贈や生前贈与以外の場面でも問題となることはありえます。また,受けた利益が実際に課税が問題になる場面で残っているのかが問題となることがあります。
こうした第二次納税義務は本来の税金を納めるべき方(引き継ぐ方を含む)が支払いをしない場面で問題となる可能性があります。一種の保証人に近い立場ということはできますが,支払いが問題になる場面では本来支払うべき方の支払い能力はないことも多いと思われますので,支払った後の回収には問題が出ることは多いものと思われます。遺贈を受ける場合に,こうしたことを問題にすることがそこまでないかもしれませんが,特に税金関係は他の負債とは異なる法律上の考慮(今回取り上げた第二次納税義務のようなもの)も存在するので,負担上限はあるにしても,注意が必要なケースはありうるでしょう。
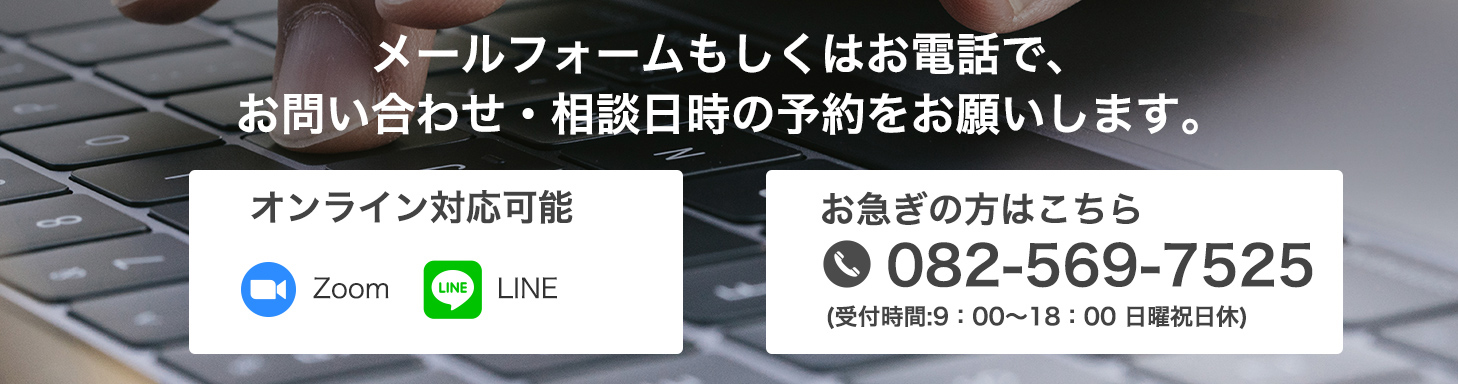
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。

© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.